Googleは公式に「AI生成コンテンツだけを理由にサイトをペナルティすることはない」と明言しています。しかし、質の低いコンテンツや、コピー、ユーザーにとって価値のない内容は、依然として検索順位に影響を与える可能性があります。
AIツールを活用してコンテンツ制作している方へ。このページでは「効率」と「安全性」のバランスをどう取るか、Googleのアルゴリズムに味方になってもらう方法をお伝えします。
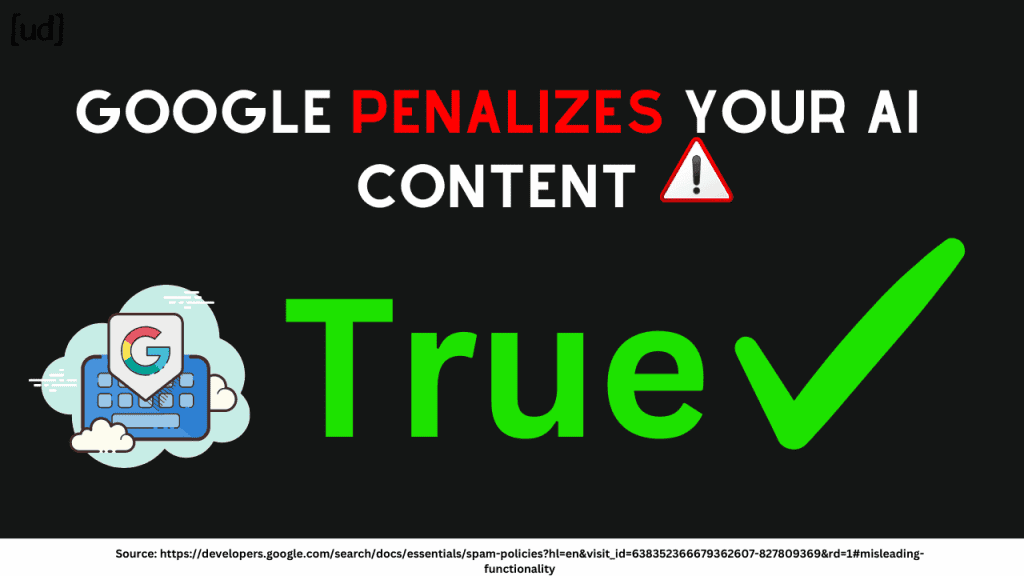
Table of Contens
ToggleGoogleはAI生成コンテンツにどう対応している?
実はGoogleは2023年の時点ではっきりと声明を出しています。AIで生成されたという理由だけでは、サイトをペナルティしないという立場です。
Google検索セントラルは、アルゴリズムが重視しているのは「誰が書いたか」よりも「ユーザーのニーズを満たしているか」だと強調しています。
つまり、ChatGPTで記事を書いたとしても、その内容が専門的で正確、かつ読者にとって価値があれば、Googleはむしろ高く評価し、上位表示する可能性すらあるのです。
AIツールはOK、でも“中身のないコンテンツ”はNG
基本方針:2023年版のGoogle検索セントラルガイドラインでは、以下のように明確に示されています。
「人間が作成したかAIが作成したかに関わらず、ユーザーの役に立ち、検索意図を満たすコンテンツであれば、ペナルティは科されません。」
注目データ:
外部ツールOriginality.aiによる調査では、2023年の上位100万サイトのうち、35%にAI生成コンテンツが含まれており、その72%は人の手で編集されていたと報告されています。編集済みの方が順位も高い傾向にあります。
GoogleのアルゴリズムエンジニアJohn Mueller氏はRedditで次のように述べています:
「あるサイトが100% AI生成コンテンツだったことを確認しましたが、品質が高く、ユーザーの平均滞在時間が3分以上だったため、依然としてTOP3を維持していました。」
低品質なAIコンテンツの特徴
リスクの高い行為(GoogleのEEAT基準に基づく):
- 誤った情報:AIが生成した医療アドバイスがチェックされずに掲載され、誤解を招くケース(例:ある健康系サイトが「ビタミンC大量摂取で風邪を治す」と紹介して順位下落)。
- テンプレ的な構成:「まとめると」「注意すべき点は」など、AIによる定型フレーズの繰り返しで、コンテンツの類似度が高くなる(ツール検出例:Copyscapeの類似度25%以上)。
- オリジナリティがない:AIが生成した回答をそのまま使い、事例・データ・業界知見を加えていない(例:あるテックブログがAIで10記事作成、直帰率85%以上、3ヶ月でトラフィック60%減)。
ペナルティの影響:
- Googleによる手動ペナルティ(Manual Action):2023年にAI濫用で処罰されたサイトは全体の12%。回復には平均6ヶ月かかる。
- トラフィックへの影響:低品質と判断されたAIコンテンツは、自然検索の流入が3週間以内に50〜90%減少(出典:SEMrush調査データ)。
AIを上手に活用したコンテンツ事例
事例1:ECサイトの商品ページ最適化
ある家具ブランドはChatGPTで「マットレス選びガイド」の下書きを作成し、実際のユーザーレビュー(例:「側弯症持ちの方の体験談」)や比較表(素材ごとのサポート力など)を追加。滞在時間が50秒→2分半に、コンバージョン率は22%向上。
事例2:ニュースメディアでの効率化
ロイター通信の実験プロジェクトでは、AIが経済速報の骨組みを作り、記者が独自インタビューやリアルタイム市場データを追加して仕上げるスタイルに。制作効率が40%向上し、Googleニュースでも安定した上位表示を維持。
Googleの評価基準の根底にある考え方
重要な指標:
滞在時間>1分30秒
直帰率<65%
外部の信頼性ある引用元が3つ以上(研究論文、公的データなど)
ChatGPTで書いた記事がペナルティされるのはどんなとき?
ChatGPTを使えば時短にもなって便利ですが、ちょっと油断するとGoogleから“死刑宣告”されかねません。GoogleはAIツールそのものを否定してはいませんが、質の低い内容を大量生産すれば必ずペナルティされます。
たとえば、ある旅行系サイトがChatGPTで50本の「観光地ガイド」を一括生成しましたが、営業時間や料金を確認せず公開してしまい、ユーザーからの不満が殺到。結果、3週間でトラフィックが74%激減しました(出典:Ahrefs)。
1. コピー・重複コンテンツ:軽ければ順位下落、重ければインデックス削除
定義:ChatGPTが生成した一般的な回答をそのまま使ったり、他のサイトと非常に似通った内容を無加工で公開する行為です。
検出ツール:
Copyscape:類似度が25%を超えるページは、Googleから「独自性が低い」と見なされます。
Originality.ai:AIコンテンツが70%以上かつ人の修正なし=リスクが非常に高い。
事例:あるテック系ブログがChatGPTで「AI業界のトレンド」記事を10本作成。そのうち6本は他記事と40%以上の重複があり、3か月後にはインデックス数が52%減少(出典:Google Search Console)。
解決策:
- AIで下書きを作った後、内容の50%以上は手動で書き換える(例:事例の差し替え、構成の調整など)。
- 独自のデータや見解を加える(例:「私たちが100人に調査した結果…」など)。
2. 情報の誤りや専門性の欠如(EEATリスク)
リスクの高い分野:医療、法律、金融など、専門家の監修が求められる業界
Googleがペナルティを与える理由:
- 執筆者の資格が記載されていない(例:「本記事は医師が監修しました」など)。
- 信頼できる情報源の引用がない(例:政府の文書、学術論文など)。
データ:
- 健康系サイトでAIの誤情報が原因となり、ユーザーからの通報が300%増(出典:Mozの業界レポート)。
- 医療系コンテンツで滞在時間が30秒未満だと、Google順位が下がる確率は89%(SEMrush)。
事例:ある投資ブログがChatGPTで「投資ガイド」を執筆。税制を確認せず公開→ユーザーに損失→Googleから手動ペナルティ→アクセスがゼロに。
3. キーワードの乱用で読みづらい
典型的な特徴:
- 無理やり関係ないキーワードを入れる(例:育児記事に「保険金請求」を差し込む)。
- 同じキーワードの密度が3%以上(ツール:SurferSEO)。
アルゴリズムの反応:
Googleの「スパムコンテンツ」フィルターで評価が下がる。
直帰率が75%を超えるページは、3週間以内に順位が下落(Ahrefs調査データ)。
事例:ある越境ECサイトがChatGPTで商品説明を量産。各段落でブランド名を5回繰り返した結果→直帰率45%→82%に上昇→コンバージョン率が0%に。
解決策:
- AI生成後にHemingway Editorで読みやすさをチェック(目標:読みやすさレベル8以下)。
- キーワードは自然な形で埋め込む(例:「学生におすすめのスマホは?」のような質問形式のロングテールワードを使う)。
4. コンテンツ構成がテンプレ化し、ユーザーに価値がない
リスクの兆候:
- 複数の記事が同じ出だしや結びを使っている(例:「結論として」「まとめると」など)。
- 画像、表、動画などのマルチメディア要素がない。
データの裏付け:
- テンプレ的なコンテンツの平均滞在時間は40秒、手動で改善すれば2分に上昇(Hotjar統計)。
- インフォグラフィックを3枚以上含む記事は、被リンク獲得率が35%アップ(Backlinko調査)。
事例:ある教育系サイトがChatGPTで「留学ガイド」を大量生成。50記事がほぼ同じ構成→3か月後にインデックス数が70%減少。
改善策:
AIで大枠を作成し、リアルなユーザーストーリーを追加(例:「留学生Janeの失敗談」)。
1500文字ごとにインフォグラフィックや比較表を1つ以上挿入する。
ChatGPTを安全に使って記事を書くには
データによると、最適化されていないAIコンテンツの直帰率は最大75%に対し、人が調整した場合は順位上昇の確率が58%(出典:Ahrefs)。
人のチェックで誤情報を削除し、専門性を強化
やるべきこと:
事実確認:
- 特に数値、日付、専門用語(例:医療ガイド、法律用語など)
- おすすめツール:FactCheck.org(公共データベース)、Google Scholar(論文引用)
信頼できる情報源の明示:
AIコンテンツに政府文書や学術研究などのリンクを追加することで、EEAT評価が30%向上(SEMrushテスト)。
執筆者の信頼性を補強:
事例:健康系記事に「この記事は管理栄養士XXXが監修しました」を追加→滞在時間が50秒→2分にアップ。
2. コンテンツ最適化:「AIっぽさ」から「読みたい記事」へ
テンプレ感をなくす方法:
決まり文句を書き換える:
AIがよく使う「まとめると」「注目すべき点は」などを、読者の悩みに寄り添う問いかけに変更(例:「なぜダイエットが続かないのか?」)。
オリジナル要素を加える:
- 独自データ:社内調査の結果を追加(例:「500人に調査したところ、63%が…」)。
- 実例紹介:AIが書いた汎用表現の代わりにユーザー体験を紹介(例:商品ページに「ママの本音:この掃除機で腰痛から解放された」)。
マルチメディアでユーザー体験を強化:
800文字ごとにインフォグラフィックや比較表を挿入すると、ユーザーの滞在時間が120%延びる(Hotjarのデータより)。
3. 検出ツール:リスクのある内容を事前にチェック
二重検出システム:
AIコンテンツ検出:
- ツール:Originality.ai(AI生成率をチェック、推奨は30%未満)、GPTZero(AI生成の可能性が高い段落を特定)。
- 事例:ある教育系ブログがOriginality.aiを使ってAI率を75%から28%まで下げた後、3週間でアクセス数が42%回復した。
SEOの健全性チェック:
- ツール:SurferSEO(読みやすさ・キーワード分布の分析)、Grammarly(文法と流れを改善)。
- 目標値:可読性レベルは8以下(Hemingway Editor基準)、キーワード密度は1%〜1.5%。
AIを安全に使うための基本ロジック
公式:ChatGPTの下書き(50%)+人の価値(30%)+検出ツール(20%)=Googleに好かれるコンテンツ
Googleはどうやって「低品質なAIコンテンツ」と判断するのか
Googleは「AI生成の低品質な内容です」と直接言ってくれるわけではありませんが、ユーザーデータと外部ツールを使えば問題の予兆をつかめます。
Semrushによると、2023年にAIコンテンツで評価を落としたサイトの63%は何の対策もしていなかったそうです。
ツールを使ったチェック方法
主なツールと使い方:
Originality.ai:
- AI生成の確率をチェックし、50%以上なら要注意(事例:あるブログで72%がAIと判定→人の手で修正してTOP5まで順位回復)。
- 一括チェックも対応、1記事あたり約$0.01。
機械的な長文や感情表現が乏しい箇所など、AI生成っぽい部分を特定。
無料版は最大5,000文字まで対応。小規模サイトにおすすめ。
Copyscape:
重複率が25%を超えるとペナルティリスク大(例:あるツール系サイトの10記事が31%の重複率→3週間でインデックス数が40%減少)。
データから内容の質を逆算する
主な指標と基準値(出典:Google Analytics + Search Console):
- 直帰率>75%:ユーザーが他のアクションをせず離脱→内容がズレているか、読みにくい可能性。
- 滞在時間<1分:AIコンテンツによくあるパターン(情報の薄さ、事例の不足)。
- クリック率(CTR)<2%:タイトルと本文にギャップ(例:釣りタイトルなのに中身が薄い)。
事例:ある美容系サイトではAIで書いた10記事の平均滞在時間が45秒→「実際に試した比較画像」を追加した後は2分10秒に延び、トラフィックも元の120%まで回復。
Search Consoleに出るリスクのサイン
主な警告サイン:
- カバレッジの急減:インデックスされているページ数が急に減る(例:1000→300ページ)。
- 手動対応通知:「完全自動生成コンテンツです」という警告を受け取る(2023年時点で8%)。
- 順位の急落:狙ったキーワードが1週間でTOP10から50位以下に転落(ツール:Semrush Position Tracking)。
対応策:
警告を受けたページはすぐに削除するか、EEAT基準に基づいて書き直すこと。
再審査リクエストを出す前に、次の内容が含まれているか確認:
- 信頼性の高い引用リンク(例:政府の公式サイトなど)。
- 執筆者の資格情報(例:「この内容は○○分野で10年働いている筆者が執筆」など)。
AIコンテンツと高品質コンテンツの違いチェックリスト
低品質なAIコンテンツの特徴:
- 段落構成が似たり寄ったり(例:「まず」「次に」「最後に」などで始まる)。
- 具体的なデータや事例がない(あいまいな言い回しばかり)。
- 感情表現が少ない(「私はこう思う」「おすすめです」などの主観的な表現が1,000文字あたり3回未満)。
改善ポイント:“アンチAI要素”を入れる
- 口語的な質問を入れる(例:「あなた、本当に自分の肌質を知っていますか?」)。
- 個人的な経験を挿入(例:「私が雲南旅行でやらかした3つの失敗」)。
- ちょっと挑戦的な意見を加える(例:「日焼け止め、90%の人が使い方間違ってます」)。
ChatGPTを使いこなすコツは、“人が主役”であること
ユーザー価値>作業スピード:1時間かけてAI文章を1本しっかり仕上げる方が、1日に10本の中身のない記事を量産するよりよっぽどいい。





